ウイメンズセンター婦人科
更年期障害を心配して来院された方へ、その検査と治療について
更年期とは?その原因は?
日本人の平均的な閉経(1年間月経(生理)がない状態)の年齢は50歳ですが、閉経前の5年間と閉経後の5年間をあわせた10年間を更年期といいます。
更年期障害は、女性が更年期に経験する一連の身体的および精神的な症状を指します。加齢とともに卵巣機能が低下し、女性ホルモン(特にエストロゲン)が大きく揺らぎながら低下していくことに関連しています。閉経はすべての女性に起こる現象ですが、女性全員が深刻な更年期障害を起こすわけではありません。さまざまな要因、例えば加齢などの身体的因子、性格などの心理的因子、職場や家庭における人間関係などの社会的因子が関与することで発症すると考えられています。
更年期の症状
更年期にはさまざまな症状があらわれることがあります。
一般的な症状には、以下のようなものがあります。
| 月経周期の変化 |
40歳代から月経周期が不規則(月経不順)になり、最終的には閉経します。 |
|---|---|
| 血管運動神経症状 |
ホットフラッシュ、ほてり、汗、冷えなど。突然の暑さや発汗を伴い、顔・首・胸・上半身全体に広がることがあります。また夜間に汗をかき、寝不足や不快感の原因になることがあります。 |
| 自律神経症状 |
動悸、息切れ、頭痛、めまい、吐き気など。 |
| メンタルヘルス不調 |
憂うつ、不安、イライラ、情緒不安定、不眠など。更年期のホルモン変化が、精神症状やメンタルヘルスに影響を与えることがあります。 |
| 疲労倦怠感 |
からだの疲労感や倦怠感が増すことがあります。 |
| 泌尿器・生殖器症状 |
頻尿、尿漏れ、外陰部違和感、性交痛など。 |
| からだの痛み |
肩こり、腰痛、関節痛など。 |
以下は、更年期とメンタルヘルスの関係についての詳細です。
ホットフラッシュや夜間の発汗などの更年期症状は、睡眠の質を低下させることがあります。不眠症は精神的な健康に悪影響を及ぼし、不安や抑うつの症状を悪化させる可能性があります。
| ストレスと対処能力 |
更年期症状はストレスを増加させることがあり、メンタルヘルスに悪影響を及ぼす要因となります。ストレスへの対処能力が低下すると、抑うつ症状や不安障害のリスクを増加させることがあります。 |
|---|---|
| 自己イメージと自己評価 |
更年期における身体的変化(体重増加、肌の変化など)は、自己イメージや自己評価に影響を及ぼすことがあります。時には自尊心の低下や抑うつ感につながることがあります。 |
| 社会的関係 |
更年期症状が社会的関係に影響を及ぼすこともあります。家族や友人とのコミュニケーションが困難になり、孤立感や疎外感を感じることがあります。 |
更年期障害の治療
ホルモン補充療法(Hormone Replacement Therapy;HRT)
ホルモン補充療法は、更年期障害の症状であるホットフラッシュなどの血管運動神経症状を緩和するために用いられます。この治療法では、不足している女性ホルモン(エストロゲン)を補充します。
| 利点 |
症状の緩和、骨密度の低下予防、心血管疾患のリスク軽減などがあります。 |
|---|---|
| 注意点 |
副作用やリスク(例: 乳がん、血栓塞栓症、心臓病の増加)があるため、医師との相談が必要です。また、適切な製剤や投与方法を決定する際にも医師の指導が不可欠です。
|
漢方療法
漢方療法は、東洋中医学の原則に基づいて、天然の植物成分を用いて心身のバランスを整え、更年期障害の症状を軽減しようとするアプローチです。漢方薬剤は、症状に応じて処方されます。
| 利点 |
一部の患者にとって、症状の緩和に効果があると報告されています。 |
|---|---|
| 注意点 |
漢方薬は一般に安全ですが、副作用や相互作用の可能性があるため、医師との相談が必要です。 |
精神科的治療
抗うつ薬や抗不安薬、睡眠導入剤などの薬物が、更年期障害の精神症状(不安、うつ症状、不眠など)を管理するために使用されることがあります。
| 利点 |
精神症状の緩和や心理的な苦痛の軽減が期待されます。 |
|---|---|
| 注意点 |
薬物療法は副作用を伴う場合があるため、医師の処方を遵守することが重要です。また、薬物治療に併用して心理療法やカウンセリングも検討されることがあります。必要に応じて専門クリニックへの紹介を行う場合もあります。 |
カウンセリングおよび心理療法
カウンセリングや心理療法は、更年期障害に伴う感情的な課題やストレスの管理に役立ちます。認知行動療法やリラクゼーションテクニックなどが一般的に使用されます。
| 利点 |
心理的サポート、ストレス軽減、自己認識向上、ストレス対処策の提供が期待されます。 |
|---|---|
| 注意点 |
カウンセリングや心理療法の効果は個人によって異なります。適切な専門家を見つけることが大切です。 |
更年期障害の治療効果には個人差があり、患者の症状や健康状態にあわせて治療計画を立てることが重要です。治療法は医師と相談のもとで選択され、定期的なフォローアップが行われます。
また更年期障害の症状を緩和するためには、食事や運動などの生活習慣の改善も大切です。
更年期の検査
更年期のホルモン、症状や年齢に基づいて適宜必要な検査を行い医師が診断します。
婦人科の悪性疾患や婦人科疾患以外の健康問題を除外し、行います。
更年期の補助診断
| 血液検査 |
下垂体・卵巣から分泌されるホルモンの検査を行って、実際に卵巣から分泌されるホルモンの減少を確認します。 |
|---|
更年期障害の症状に関する問診票への回答
「簡略更年期指数」にお答えの上、お待ちください。
婦人科疾患以外の健康問題を排除するために必要な検査
更年期に出現する症状が、内科的疾患に起因することがあります。例えば、疲労感や倦怠感が甲状腺機能低下によるものであったり、めまいが耳の異常であったり、頭痛が脳の異常であったりすることもあります。そのため、婦人科以外の疾患が疑われる場合には、婦人科のみならず検査を行い、これら疾患を除外する必要があります。必要に応じて他科の医師に依頼することもあります。
| 目的 |
腹部、外陰、腟、子宮、卵巣の健康状態を確認します。 |
|---|---|
| 内容 |
腹部を触診で診察し、緊急対応の有無を確認します。外陰部の状態を観察し、次に腟鏡を用いて腟内と子宮頸部を調べます。少し違和感はあるかもしれませんが、通常、痛みは伴いません。 ![[写真]](/images/department/gynecology/pht_examination-table.webp?20240413) ![[図]](/images/department/gynecology/fig_vaginal-mirror01.webp?20240413) ![[図]](/images/department/gynecology/fig_vaginal-mirror02.webp?20240413)
|
| 目的 |
子宮頸部の細胞を採取し、異常がないか調べます。 |
|---|---|
| 内容 |
子宮頸部から細胞をブラシで軽くこすり取り、顕微鏡で検査します。悪性腫瘍(がん)の有無を確認します。年齢や症状よっては、体がん検査も追加します。特にホルモン補充療法を考慮されるような場合には、ホルモン剤の影響で子宮内膜の病気を悪化させる恐れがあるために、体がん検査を行い、異常のないことを確認したのちにHRTを開始します。 ![[図]](/images/department/gynecology/fig_cancer-test.webp) |
| 目的 |
内診ではわからない、子宮内部や卵巣の形態上の異常がないか確認します。子宮や卵巣の異常、卵巣の腫れや嚢胞、子宮内膜の状態などを評価します。 |
|---|---|
| 内容 |
腹部または腟内に超音波プローブをあて、内部の画像を取得します。 ![[図]](/images/department/gynecology/fig_ultrasound-examination.webp)
|
|
甲状腺などの内分泌疾患や閉経後に増加する脂質異常症、耐糖能異常、泌尿器科疾患を調べるために血液や尿検査が行われることがあります。 |
|
乳がん検診は、日本では40歳以上を対象に、2年に1回、問診・視診・触診および乳房X線検査(マンモグラフィ)が行われています。加えて自分で乳房を触診し、しこりや異常を評価する自己乳房検診も毎月行うことが推奨されています。ホルモン補充療法を受ける可能性のある方は乳がん検診が必要です。
|
| 目的 |
女性ホルモンの低下によって起こる骨密度の減少を確認したい場合に行います。骨粗しょう症により、背骨(椎体)で圧迫骨折が起こると身長が縮み、前かがみの姿勢になります。また大腿骨(足の骨)が折れると、将来の寝たきりの原因にもなります。 |
|---|---|
| 内容 |
DEXA法(Dual Energy X-ray Absorptiomentry)は2種類の異なるエックス線を照射し、骨と軟部組織の吸収率の差で骨密度を測定する方法です。 被曝量は極めて少なく、迅速かつ精度の高い測定ができ骨密度測定の標準とされています。 |
| 目的 |
頸動脈の状態をチェックすることで、動脈硬化を早期に発見し、動脈硬化性疾患の予防につなげます。 |
|---|---|
| 内容 |
首に超音波をあて、頸動脈のつまりや狭窄の有無を調べます。被曝はなく、からだへの負担は少ない検査です。女性ホルモンは、血管壁に付着した余分なコレステロールを取り除く善玉コレステロール(HDLコレステロール)を増加させ、悪玉コレステロール(LDLコレステロール)を低下させる働きがあります。更年期の女性ホルモン低下により、LDL-コレステロールの上昇とともに、動脈硬化が進むことになります。 |
|
CT検査は、身体の内部を詳細に見るための特殊なX線検査です。 検査の前に、過去の造影剤アレルギー反応の有無などについて医師に伝えてください。
|
|
MRI検査は、磁気を用いた画像検査です。 検査の前に、過去の造影剤アレルギー反応の有無などについて医師に伝えてください。
|
患者さんへのアドバイス
検査前には、医師に現在の症状や既往歴、服用中の薬などについて詳しく伝えてください。
検査中はリラックスし、不安や疑問があれば、遠慮なく医師や看護師に相談してください。
検査結果に基づいて、医師から提案される治療法や、次のステップについての説明を受けます。
検査結果の理解や治療選択においては、疑問や懸念を医師と共有し、納得のいく形で進めることが重要です。
初診の方へ
ご来院頂く前にご自身の症状に合わせてご一読ください。

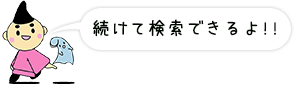
![[図]](/images/department/gynecology/fig_menopausal-disorders01.webp)
![[図]](/images/department/gynecology/fig_menopausal-disorders02.webp)